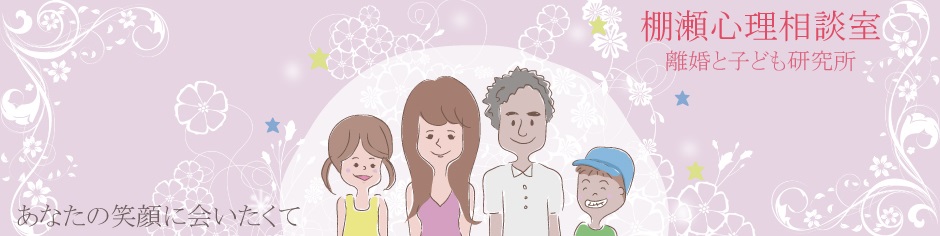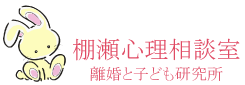今日は病院のベッドから投稿しています。「気胸」の診断を受け、胸腔内にチューブを入れて空気を抜くこと今日で3日です。ところがチューブが意図したところに入っていなかったために、ブラインドで入れるのではなくてレントゲン撮影しながらもう一度入れ直すと今朝になって言われ、少々落ち込みました。この3日間の苦労は何んだったのかと・・・。しかし、病院拘束されチューブに繋がれたために仕事ができない代わりにありあまる時間を手にしたと考え、有効利用しようと思考転換しました。というわけで「離婚とストレス」(2)です。
前回、離婚が子どもに悪影響を与える緒要因の内でも子どもに最も高いストレスを与え、深刻なダメージを与えるのは、両親間の長引く葛藤とその狭間に置かれることだとの認識がなされるようになっていることに触れました。
両親間の葛藤が長引くと、調停でやっと面会交流の合意に達しても、裁判所の手を離れた後に、監護親の癒されていない不安感、傷つき体験、怒りなどから約束が守られなかったり、面会交流中の不慮の事故などを理由に面会交流が中断されたり、何回か和やかな密度の高い交流がもたれた後に、突然、子どもから手の平を返すように「もう会いたくない!」と宣言されてしまうといったケースも多いのが現状です。
日本の裁判システムでは、面会交流の合意を強制するシステムとしては間接強制(罰金)があるのみですので、こうした問題が米国より深刻かつ頻発しているのが現状です。
こうした問題は、米国では1980年代から大きな問題として認識されてきました。当時は、怒りに満ちた監護親と白黒をはっきりさせる年代の子ども(9歳~12歳)との間の病理的な同盟の結果であると説明されてきました。その後にガードナーによって片親疎外症候群(Parental Alienation Syndrome PAS)として説明され、この言葉が米国で広く使われるようになり、近年は、日本でも裁判上の争いで用いられることが増えてきています。
しかし、この「症候群」という用語に対しては、その後、診断学上の「症候群」に該当しないとして批判が強まり、現在では「片親疎外」「疎外された子ども」、「親子疎外」などの言葉が用いられるようになっています。
日本の裁判所でも最近は、面会交流の子どもにとっての意味を監護親に説くようになってきていますので、親自らが面会交流に真っ向から反対することは難しくなってきています。代わって、親は別居親と会って欲しいと思い、努力しているが、「子どもが嫌がっている」と主張するケースが非常に増えてきています。
面会交流が今後ますます定着するにつれて、両親間の葛藤を下げる努力をしない場合には、子どもが「自らの意志」として別居親との接触を、別居前の関係性から考えて非現実的なまでに否定的な態度で、頑なに拒否する病理的なケースが増え続けるものと思います。
次回からは、そのような「片親疎外」「親子疎外」のケースにどのように対応していったら良いのかを考えていきたいと思います。